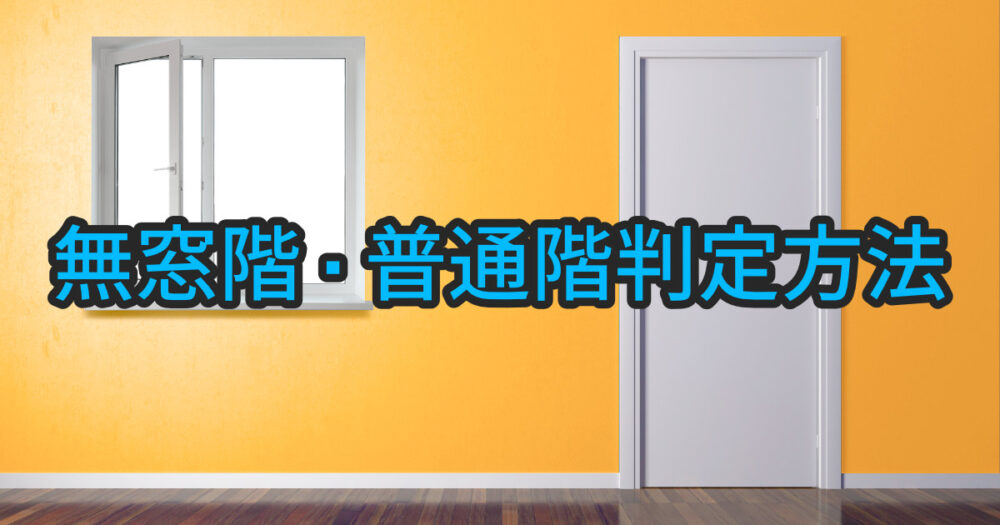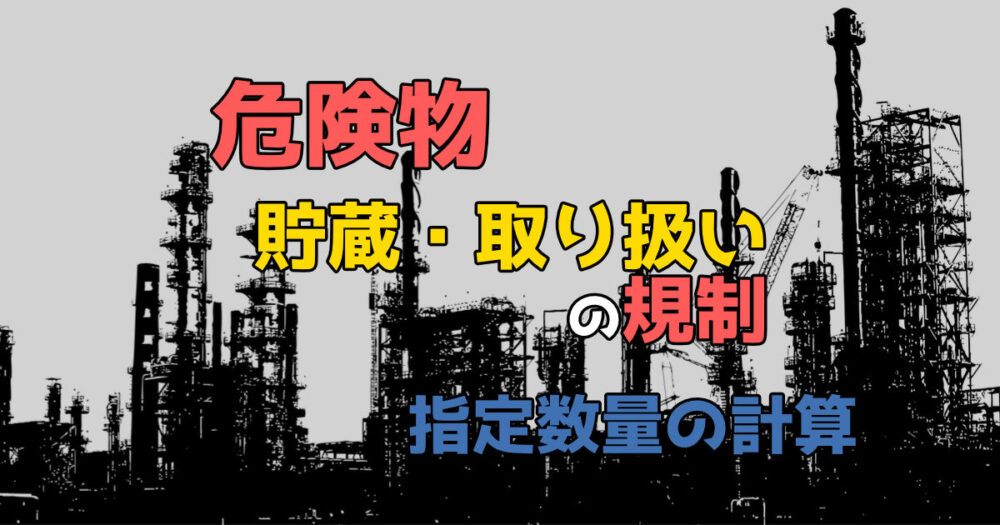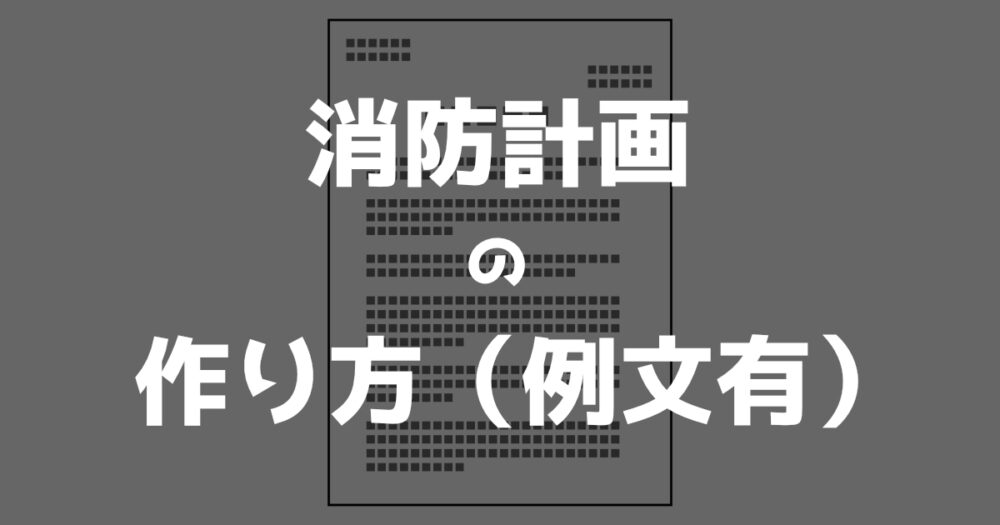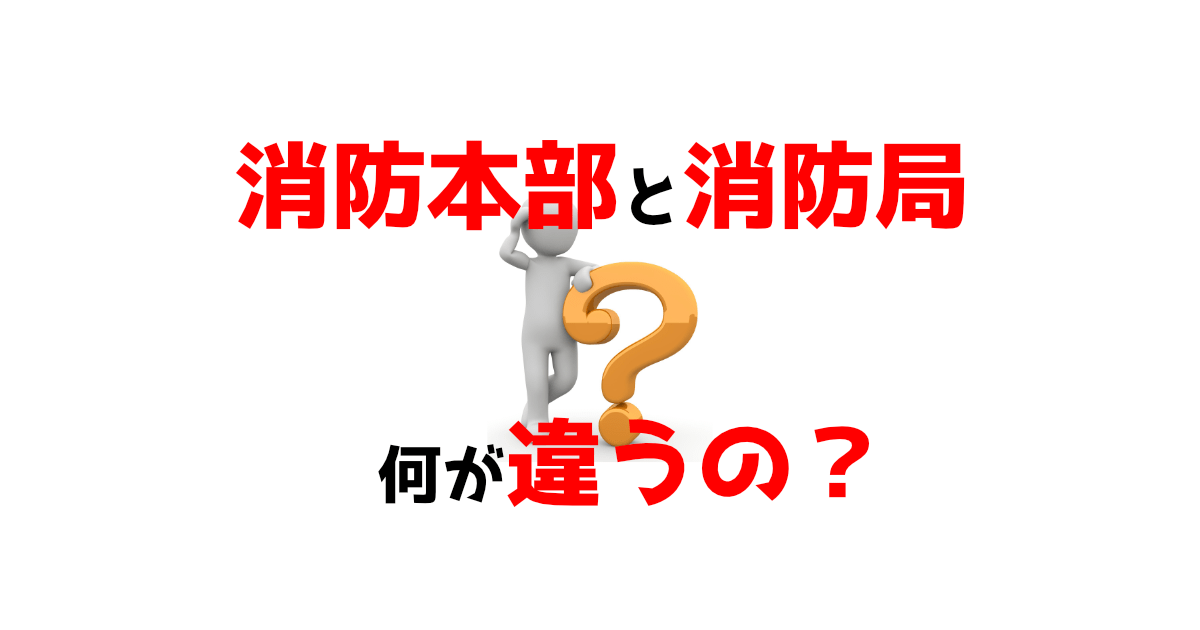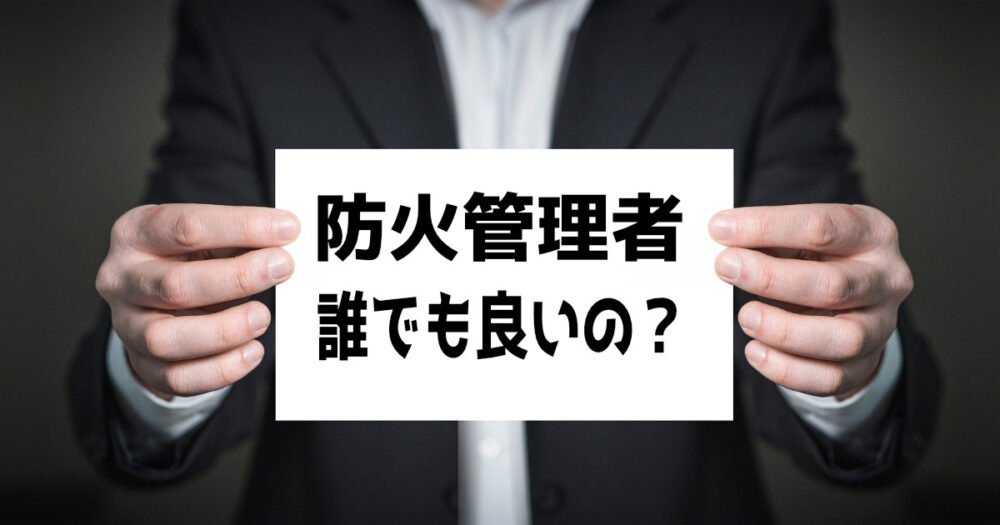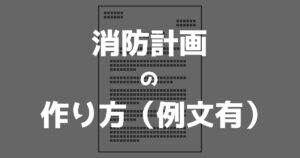防火管理者は、防火管理者となる資格を持っている人の中から、防火管理に関わる業務の推進役として管理権原者から選任された人のことです。
管理権原者とは社長など、その建物に対してすべての責任権限を持っている人のことをいいます。
例えばチェーン店の店長の場合、お店に関して責任はあるけど、グループ全体として本社の社長が権限を持っているので、管理権原者は本社の社長になります。
 クマ
クマ管理権原者は社長とかの決定権のある人物だと思えば良いです
防火管理者は、建物の火災予防などに関しての権限を持ち、通常時は火気の管理や避難通路の維持管理など重要な存在です。
そのような重要な存在なのに平社員や新人などを任命してしまうと、指示や命令が出せないことも多いので防火管理者には指示命令が出せる「管理的監督的地位にある人」を専任しなくてはいけません。
新人が訓練をしましょうと言っても業務が忙しいなどと言われてしまうかもしれませんが、部長や店長に言われたなら断れないですよね。
防火管理者は指示・命令ができる人を選任する
管理権原者が防火管理者を選任するにあたって、資格を持っているからといって平社員やアルバイトなどに防火管理者として選任してはいけません。
なぜなら、管理権原者へ防火に関する報告や意見を具申して、より良い防火管理体制を作らないといけませんし、従業員などへ命令や指示を行わなければなりませんので、必然的に管理的または監督的な地位の人が防火管理者に選任されないといけないのです。
消防へ届け出する防火管理者は、代表者が同じ大きな会社なら1人です。部署ごとに選任して届け出する訳ではありません。
また、管理権原者が防火管理者を兼任しても問題ありません。
防火管理制度
もしも火災が発生した場合、なるべく早く発見して小さい火のうちに消火できて避難することができれば一番良いことです。
消防法では一定規模以上の建物に自動火災報知設備やスプリンクラーなどを設置して維持する義務を持たせています。
ですが自動火災報知設備やスプリンクラーといったハード面は、火災予防の視点から見ると十分ではありません。これらは火災が起きた後に役にたつもので、そもそも火災が発生しないようにする人的な面、ソフト面の充実が大事なのです。
人的な面で建物の防火管理、つまり火災予防の責任を持たせて火災を出さない、出しても被害を小さくしようとしてるのが防火管理者制度です。
防火管理者の選任が必要な建物
簡単に説明すると病院、学校、工場、事務所、共同住宅、飲食店、スーパーなどなど社員や住民、利用者などが一定の人数以上居る建物が防火管理者の選任対象となります。
- グループホームのような施設 10人以上
- カラオケ、飲食店、病院、ホテルなど 30人以上
- アパート、学校、工場、事務所など 50人以上
他にも収容人員が50人以上、新築工事中の階数11階以上で延べ面積1万㎡以上の建物、延べが5万㎡以上の建物、地下面積が5千㎡以上の建物、建造中の旅客船で甲板数が11以上のものとかがありますが、今回は普通の建物のみ説明します。
防火管理者の種類
防火管理者の資格を一般の人が取ろうと思った場合、市町村の消防本部か日本防火協会が実施している防火管理に関する講習を受講して、修了したら「乙種防火管理者」か「甲種防火管理者」の資格を取ることができます。
基本的にはどこの自治体も平日に行っているので、講習を受講する場合には会社を休むことになると思います。
- 乙種防火管理者は1日
- 甲種防火管理者は2日



誰でも受講できる?



受講自体に制限はないので、誰でも受けることが出来ます
甲種と乙種の違い
防火管理者として、やるべき仕事は乙種も甲種も同じですが、建物の収容人員や面積で選任できる防火管理者が変わってきます。
甲種防火管理者は、すべての建物で防火管理者に選任することが出来ます。
乙種防火管理者が選任できるのは、次の建物です。
- 6項ロ以外の特定防火対象物で収容人員が30人以上で面積が300㎡未満の建物
- 非特定防火対象物で収容人員が50人以上で面積が500㎡未満の建物
防火管理者が不在になる期間がある場合
異動の時期や防火管理者が突発的に退職した場合、防火管理者が不在になる期間が発生することもあります。
こういった一時的に防火管理者が不在になる期間があるとき、私の指導としては次のようにしていました。
- 管理権原者や建物の責任者が防火に関して責任をもつ
- 従業員や社員に対して火災予防の徹底を強化する
- 防火管理に関する講習を受講したら、すぐに選任する



諸事情により一時的に不在となることは仕方ないので、不在の間はいつも以上に火災予防をしっかりするようお願いしていました。
当然講習を受けない場合には書面で通知します。
まとめ
防火管理者は建物の火災予防に関してソフト面を担っています。会社の誰を選任して良いわけではなく、他の社員に指示・命令のできる地位の人でなければいけません。
防火管理者は選任後に消防計画を作成して届け出しないといけません。
こちらの記事を参考にしてください。
防火管理者のしないといけない訓練についてはこちらです。