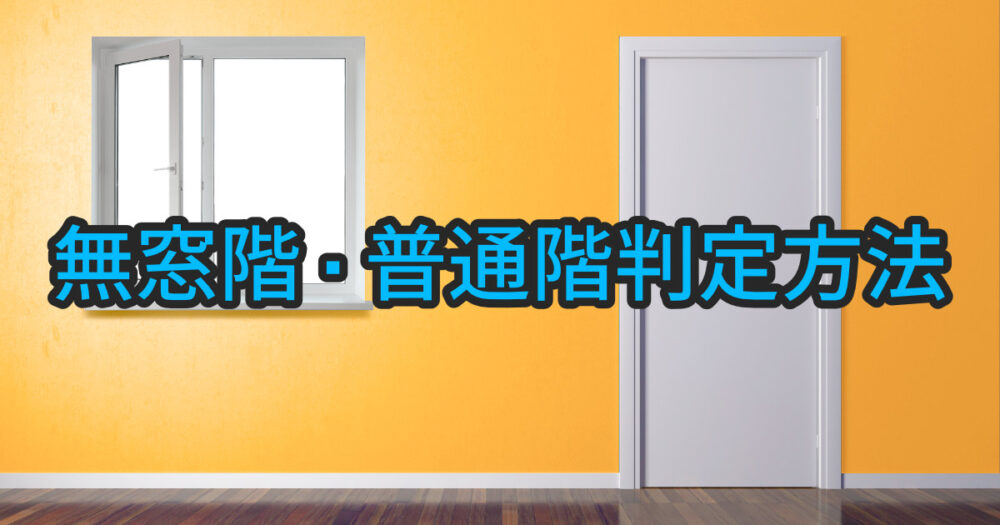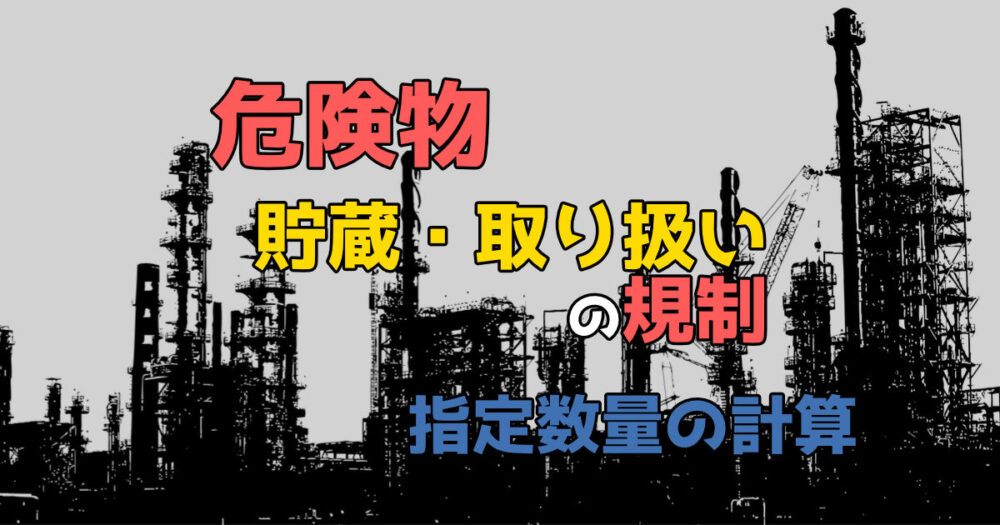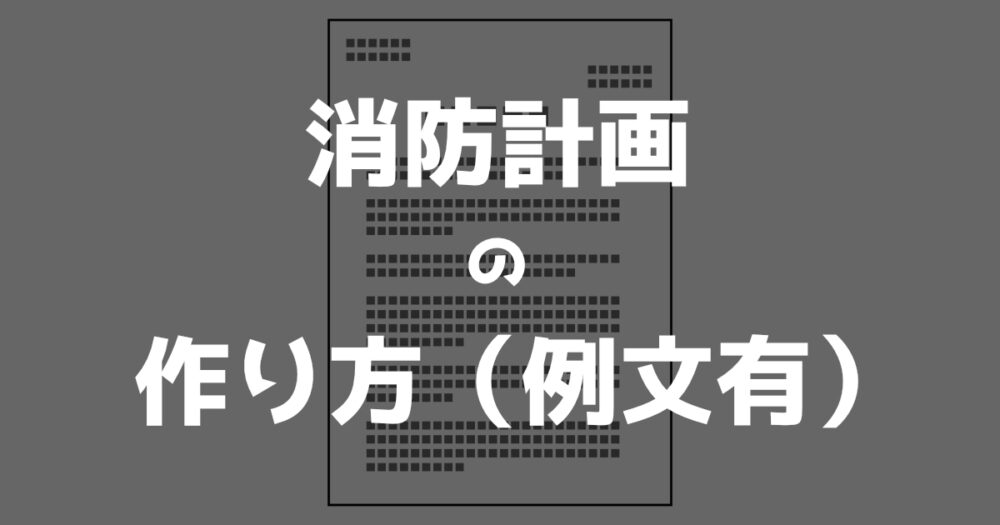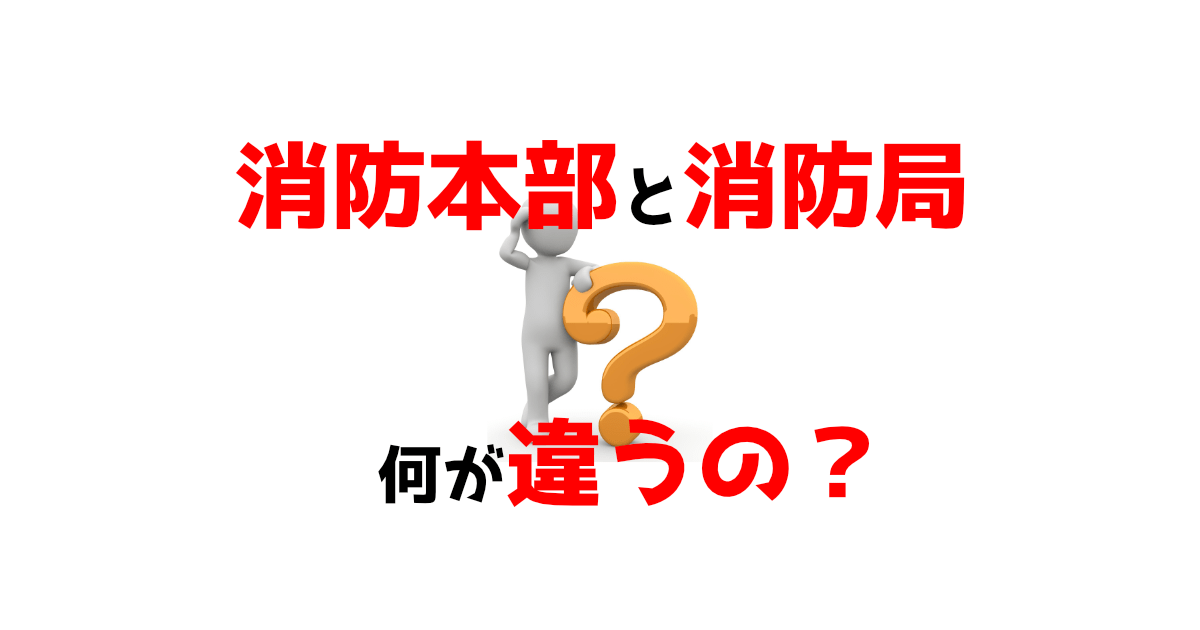消防士じゃなくても消防車や救急車の緊急走行をしてみたいって思う人もいるでしょう。
消防に採用されたら消防車や救急車を運転してみたいですよね?私は早く運転したかったです。
消防車や救急車って何か特別な免許が必要な気がしますよね?
はしご車なんかは大きいし、はしごを伸ばすので免許が必要そうです。
 クマ
クマ運転するだけなら自動車免許があれば良いです
この記事では消防車両の運転について解説します。
自動車免許があれば誰でも運転できる
消防車の運転は、中型車や大型車など消防車のサイズに応じた自動車免許があれば良く、救急車は普通免許で運転できます。
はしご車も、大型特殊のような特別な免許も必要ないので、大型自動車免許があれば良いです。
はしご車は火災現場ではしごを伸ばして活動するから特別な免許が必要じゃないの?って思うかもしれませんが、道路運送車両法施行規則に大型特殊車の定義があって、そこにはしご車が当てはまってないので大型自動車免許だけで運転できるのです。
- クレーン車
- ブルドーザー
- ロードローラー
- シャベルカー
- 除雪車
- トラクター
運転はできるけど
消防車両の運転をするだけなら・・・というのも緊急走行をしないなら、一般の車と同じだからです。ただの赤いトラックですね。
官公庁オークションに消防車が出品されているのをご存じですか?
そういったオークションなどで手に入れることができれば、あなたも消防車をすぐに運転することができるのです。しかも消防車ならポンプ付きなので、放水もできちゃいますね。
消火栓などの消防水利を勝手に使用した場合罰則があるので使用しないでください。
消防士あるあるで、コカ・コーラのトラックが消防車に見えることがあります。
緊急走行するための資格
サイレンを鳴らし赤色灯を光らせ走るにはどういう資格が必要になると思いますか?
実は運転免許証以外には消防車や救急車を緊急走行で走らせるために、国家資格のような特別な免許はないのです。
じゃあ消防に入れば誰でも緊急走行しても良いのかというと、そうではありません。
機関員になる
一般的に消防では、運転手のことを機関員と呼びます。この機関員になってはじめて緊急走行を許されるのです。
機関員って資格じゃないのか?って思うかもしれませんが、各消防本部で機関員になるためにある程度の基準を作って、訓練をしたり法律や緊急走行の心構えなどを勉強したりするだけで、これといって国から基準が示されているわけでもなく、資格として履歴書にかけるようなものは一切ないんです。
機関員の区分
私が勤務していた消防本部では、機関員のランクをA~Eの5段階にわけて、それぞれ運転できる車両を決めていました。
これは運転免許証の区分が平成29年3月から「普通、準中型、中型、大型」と4種類に細分化されたためで、平成29年3月以降に免許証を取った新人は、ポンプ車も運転できないという事態になったからです。
水を積んでいない小さなポンプ車は通常4トンの車両ですが、新区分の普通免許では3.5トンまでなので運転できません。細分化される前までに免許を取っていたら、5トンまで普通免許で運転できるのでポンプ車は運転できたのです。
まとめ
消防車や救急車を運転するだけなら、車の大きさにあった免許を持っていたら運転できます。
緊急走行をするとなると、各消防本部が定めた訓練や教養を積んで許可を得た者が機関員として緊急走行できるようになるのです。