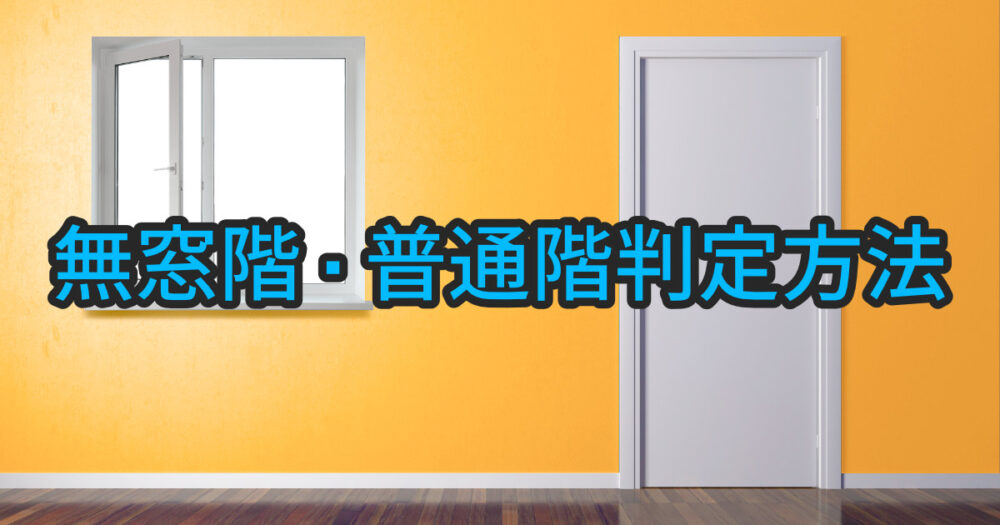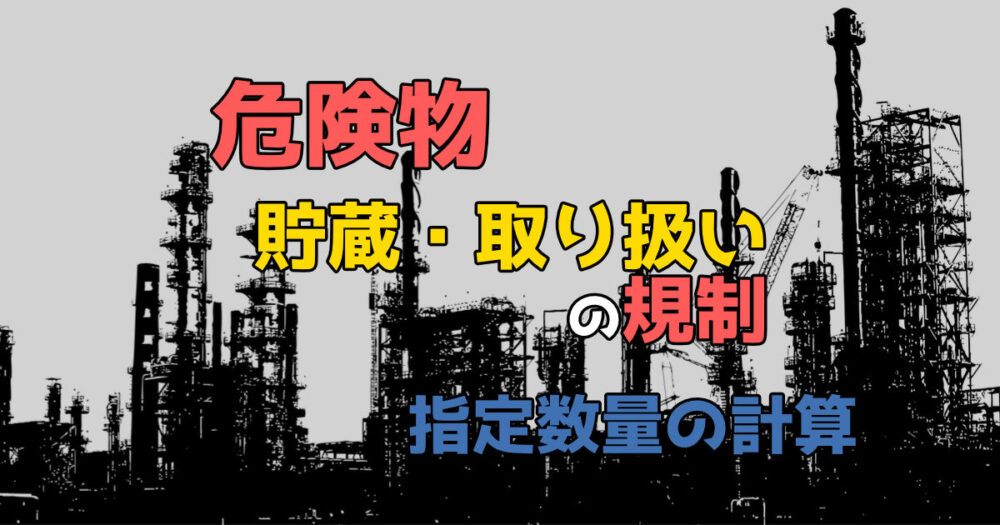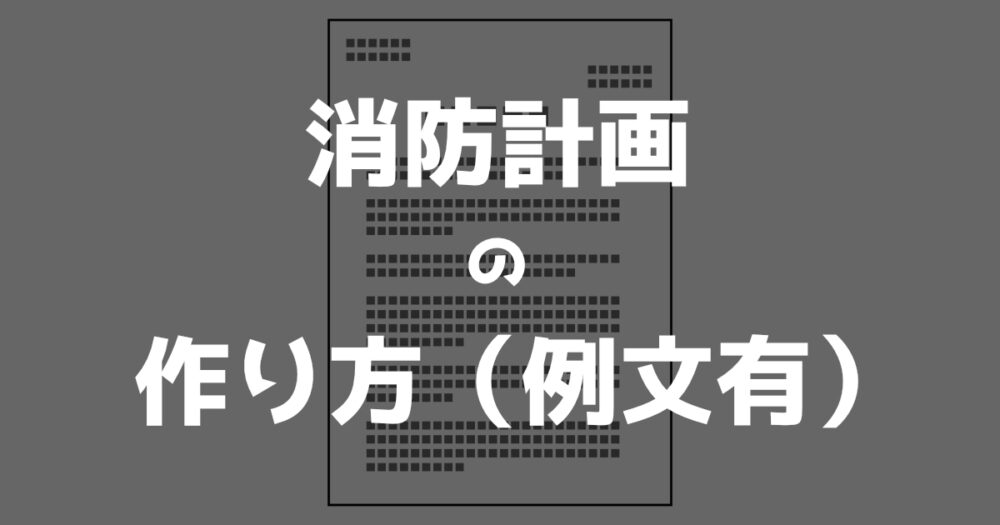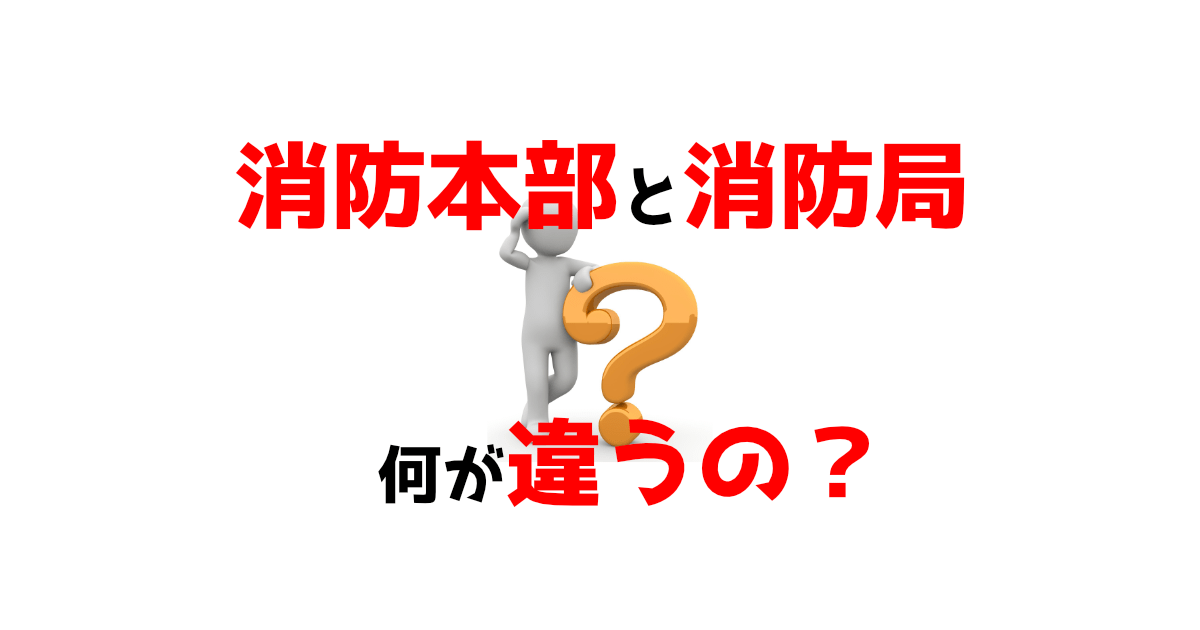消防の任務
消防の任務と言われたらどのようなことを思い浮かべますか?
火事を消す。救急、救助をするとかでしょうか?確かにそれらで正しいのですが、消防も公務員なので、しっかり任務について法律で定められています。
その消防の任務について示されているのが消防組織法 第1条です。
たったこれだけの文書に消防の任務としてのすべてが記されているんです。
消防に興味があってこのブログに来られた方の中で、もし消防士として採用されたら、この消防組織法は覚えておくと良いかもしれませんよ。私が消防学校に入校した時には暗記するテストがあったからです。
消防の組織
消防は基本的に市町村単位の組織で、警察のように県単位での組織ではありません。
複数の市町村で広域消防本部となっている所もあります。
市町村の消防に関する責任
組織法6条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
消防機関
組織法9条 市町村は、消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
消防本部
消防署
消防団
この3つのうち全部又は一部を設けなければなりません。ですが、消防署があって消防本部がないというのはできないので、消防本部がなく、消防署がある場合は広域化している場合ですね。
消防本部
各市町村の消防に関する事務を行う組織で、主に人事や庶務、装備の更新などその消防本部全体の管理を行います。
消防署
消防活動の基本となる場所で、消防車や救急車も通常はこの消防署に配備されており出動します。
また、消防署には出張所や分署、分遣所といった建物もあります。
消防団
非常勤の公務員で、普段はそれぞれ普通の暮らしをしていますが、火災時や災害発生時には消火活動に従事したり、住民の避難誘導なども行います。
特に自分たちの街は自分たちで守るという自主防災の観点からも、消防団は必要とされています。
消防本部及び消防署、消防職員
市町村単位で組織されているため、消防本部の位置や管轄区域、職員の定員は市町村条例で定められています。
定員が定められているので、大体の消防本部は退職者の人数分しか採用しないため、退職者が少ない年は採用人数も少なくなり狭き門となります。
タイミングが良ければ、退職者が多く採用倍率が低いってこともあるので、どこの市町村でも良いので消防士になりたいって人は色々と調べてみると良いと思います。
消防の広域化
市町村単位で消防は組織されていると言いましたが、国としては広域化して消防本部の数を減らす方向で進んでいます。
大災害に対して小さな市町村の消防だけでは対処しきれない場合もあります。近年では緊急消防援助隊が毎年のように派遣されていますが、消防組織そのものを合併により大きくすることで小さな消防本部が単独で対処するよりも、効率的かつ合理的に活動できるようになるからです。
実際にはなかなか広域化は進んでいませんが、指令センターの共同化等は進んでいるようです。
無線形式がアナログからデジタルに移行して設備への予算とかを考えたら指令センターの共同化もうなずけます。
しかし、指令センターの職員は知らない街の119番通報を受けなくてはならなくなり、その負担も大きくなっているのも事実です。