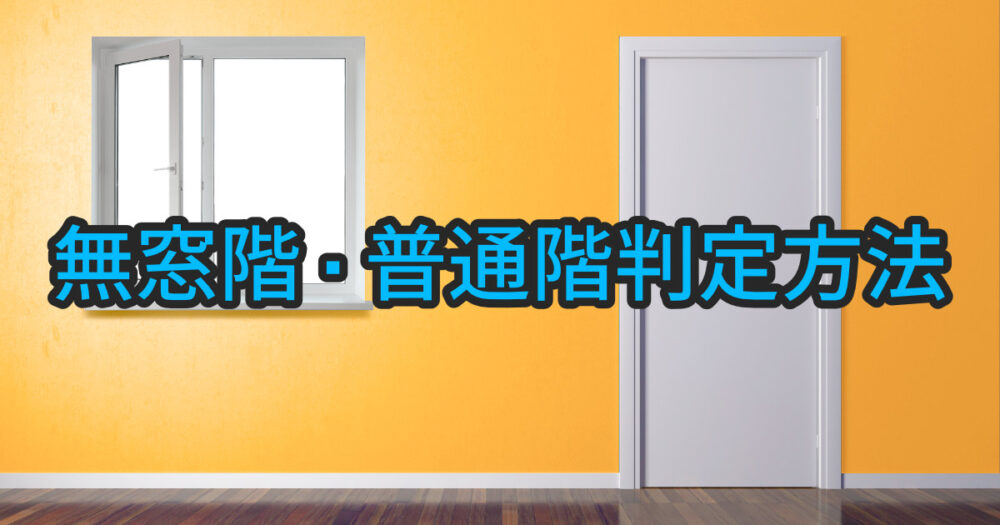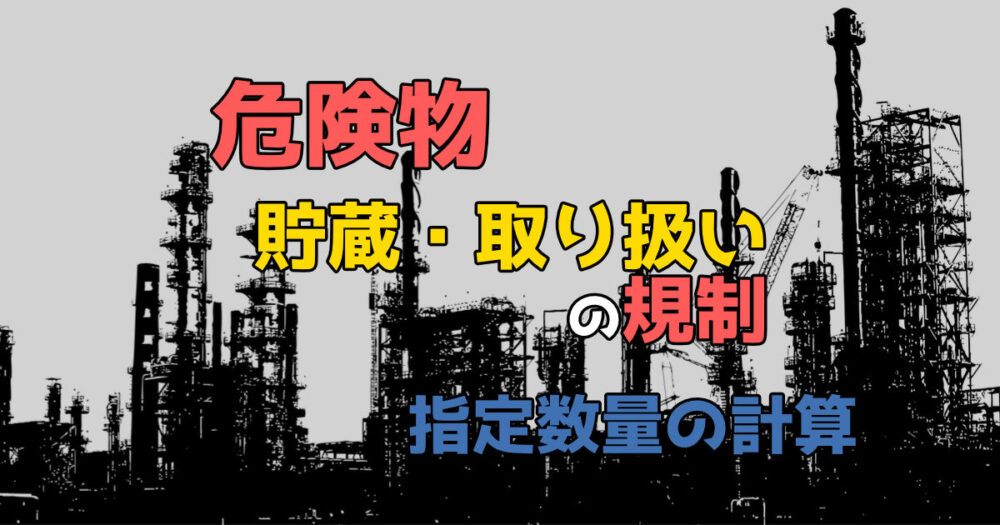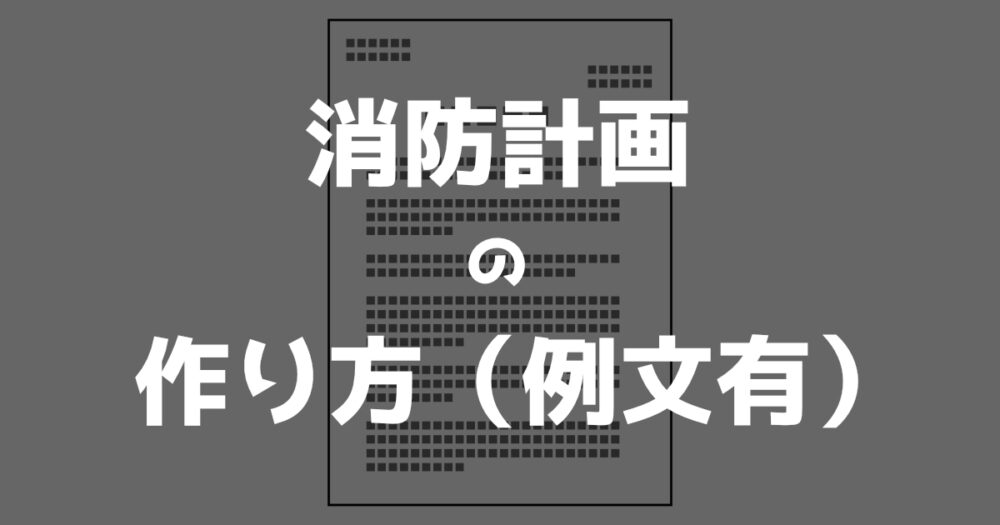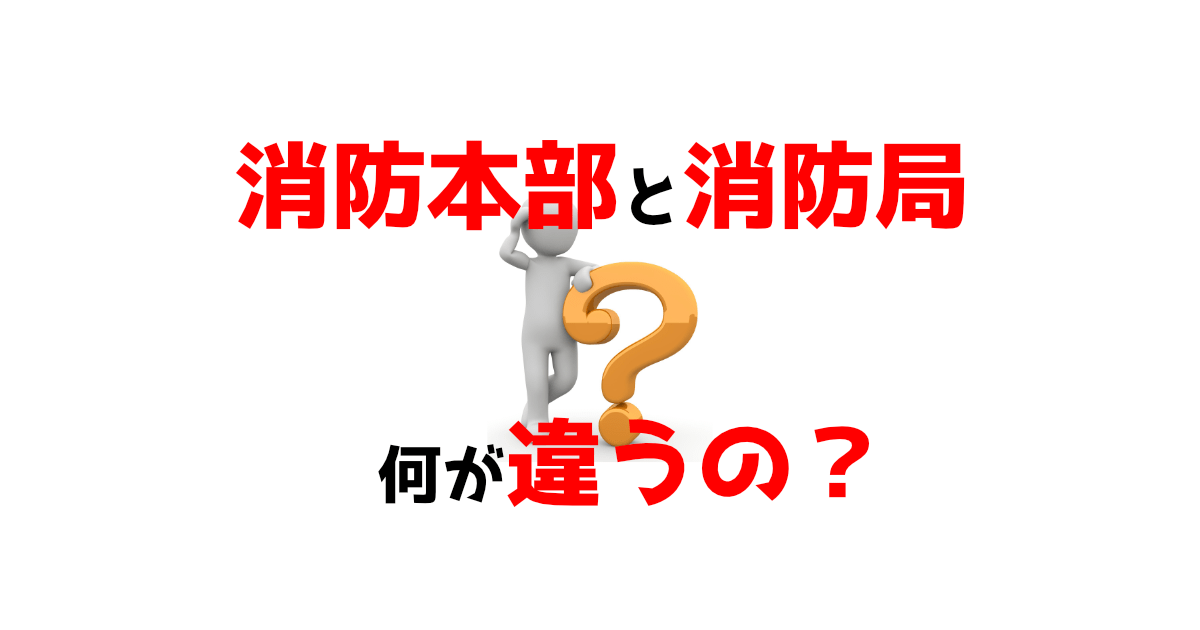地域によって○○消防本部とか○○消防局とか名前が違いますが、この違いってなんだか知ってますか?
それに消防組織の1番偉い人のことを消防長と言ったり消防局長といったりしてて、何が違うのか?って思いませんか?
この記事ではそんな疑問にお答えします。
消防本部と消防局は何が違う?
平成30年4月1日現在、日本には728もの消防本部がありますが、その中で75ほど消防局とつけている本部があります。
約1割の消防本部が消防局としていますね。
それで、何が違うのか?ってことですが、特に名前による違いはありません。
令和3年4月1日現在、総務省消防庁の消防白書のデータによると消防本部の数は724と4本部ほど減っています。
消防本部しか書かれていない
そもそも消防本部はどの法律で定められているかというと、消防組織法です。
消防組織法の第6条に
市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
市町村は自分の街は自分たちで消防業務を行いなさいっていうことですね。
消防組織法第9条には
市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
一 消防本部
二 消防署
三 消防団
ここで消防本部と出てきました。
 クマ
クマ条文に一切消防局って名称は消防組織法の中には出てきません
なぜ消防組織法に消防局って名称が出てきていないのに、日本各地に○○消防局が存在しているかというと、次の条文が教えてくれます。
消防組織法第10条です。
消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域は条例で定める。
2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
ここで重要なのは、名称を条例で定めて良いってことですね。
市町村の好きにして良い
消防の名称は、それぞれの市町村部局の実情に合わせて名称を自由にして良いのです。
市の規模がある程度大きいと、市の組織全体の部署を市長が全部掌握するのは大変だし労力の無駄ですよね。
そういった場合、仕事内容が市役所の行政部門よりも独自性のあるような部門を◯◯局として独立組織にして権限を与えることで業務の効率化を図ることができます。
消防だけでなく、水道や港湾、道路、清掃のような部門ですね。
小さいな市町村だと、これらの名称も○○部とか○○課ってなっているはずです。
他の行政部門が水道局や清掃局のように、○○局としたら、消防も市の組織の1つなので、他に合わせて消防本部じゃなくて消防局としているのです。
少し特殊なのが、東京消防庁で、東京23区すべてを管轄しているので、組織規模が他の消防本部とは違い大きいので庁がついてます。
庁より大きいと省になって国レベルになりますね。
横浜市は今でこそ横浜市消防局って名前ですけど、2006年4月1日から2010年3月31日までの間は横浜市安全管理局って名前を採用していました。
当時は消防のしの字もない名前になったのを聞いて、横浜はやっぱり独自性があるなぁって思いました。
消防局長も法律にはない?
消防長に関して書かれているのは、消防組織法第12条で
消防本部の長は消防長とする。
2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を式監督する。
これだけしか書かれていません。消防組織法では消防長としか書かれていないんです。
消防長についても、消防本部と同じように消防長と消防局長に立場上の違いはありません。あるとしたら、消防本部の規模によって消防長の階級が違うだけです。
東京消防庁は最高階級が消防総監ですが、消防総監も階級の1つなので東京消防庁もトップは消防長です。
まとめ
消防組織として○○局の方が上とか下ではなく、市町村ごとの部局名に合わせて消防本部でも消防局でも呼び名を自由につけて良いことがわかったと思います。
ですが、だいたいの場合が市町村規模の大きいところが○○局としているので、局とついていた方が消防の規模が大きいと考えて間違いないでしょう。
消防本部(局)の規模によって階級も違うので、こちらの記事では階級について書いています。